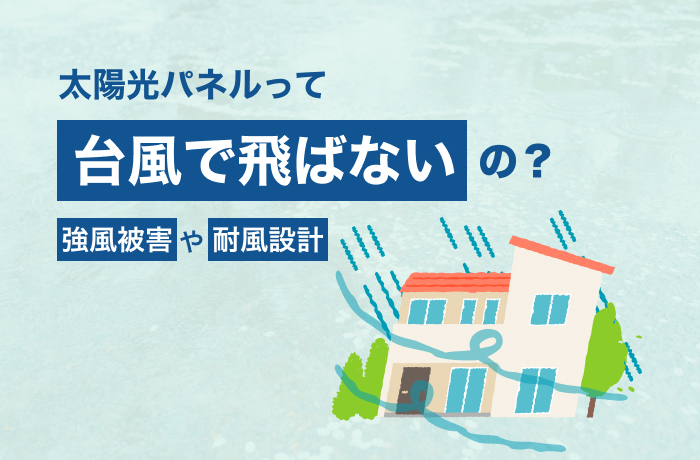
今後エネルギー不足が予想される中、エコなクリーンエネルギーとして、太陽光発電が注目されてきました。
日本におけるソーラーシステムの普及率も過去10年をさかのぼると、約15倍以上にもなっています。需要も増加し、一般家庭においても、住宅用太陽光発電が珍しくなくなったと言ってもいいでしょう。
しかしその一方、強風によるソーラパネルの被害は実際に存在しており、構造設計や耐風設計などを見直さなくてもよいのでしょうか?
そこで、ここでは耐風設計の現状と課題について考えましょう。
電気代に悩んでいませんか?
「暖房シーズンは電気代が不安!」
「細かい節電テクより大きく節約したい!」
「節約効果がずっと続く方法は? 」
太陽光発電なら 0 円の電気で何十年も節約できます!
お得に買うなら一括見積り!
- 一括見積り 10 年以上のプロが審査した優良企業を紹介!
- 良い見積もり額がなければ契約しなくて OK !
- 困ったときはいつでも電話相談できる!
現在のソーラーシステムの耐風安全性
太陽光発電を実際に使っている、現在設置済の住宅やメガソーラーの現状から、耐風安全性などは実際に疑問視されてきました。
しかし、安全性においては日本工業標準調査会が「太陽電池アレイ用支持物設計標準」(JIS)を定めており、それに基づいた設計が多く、数字上は問題が無いと言えます。
「安全性」を見た場合、基準内でおさまっていると言う意味では耐風設計に問題はないと言えますが、実際はどうなのでしょうか?
実際の強風被害状況はどうなの?
メガソーラーの様な大規模ソーラーシステムが飛ばされる強風被害は、数件ですが発表されています。住宅用のソーラーパネルも例外ではないのでしょう。
多くの太陽光発電に関する知識を持った施工店や業者などは、JISに定められた安全性を持って施工しています。
しかし、中にはしっかりとした耐風設計がなされていない場合(悪徳業者などの知識のない施工会社の設計など)、大きな被害を招いている可能性もあります。
普通の施工店(優良施工店)なら、自然災害が起こった際の保険や、自社による補償でカバー出来ますが、「設置したら後は知りません」という様な施工店であれば復旧は自腹となります。
こういった業者のソーラーパネルなどが、大きくメディアなどで取り上げられることで被害が余計に問題視されているのかもしれません。
耐風設計の現状
しかしながら、JISの基となった実験はかなり以前に行われたものであり、当時は現在の様な急激なメガソーラーや大規模工場の屋上設置型太陽光発電システムなどは考えられていませんでした。
今ではメガソーラーなど、限られた敷地で発電量を最大にするため、モジュールの設置匂配を5度、10度にするところも多いですが、JISでは設置匂配15度以下は対象にしていません。結果的に風荷重をかなり過大評価していると言えます。
また、JISの屋上設置型モジュールの風力係数は、地上置型のものと同じ値とされています。しかし、場所によっては風量の変化は明らかで、最近の研究結果ではJISをそのまま適用するとモジュールの風荷重を過小評価する場合があることも明らかにされています。
例えば20年前からソーラーシステムの施工を行っている様な老舗店では当たり前の様に対策されている事でも、1年前に開業した新規会社では難しい事なのかもしれません。
耐風設計のこれからの課題とは?
今後、国内でも増えるメガソーラーなどの大規模太陽光発電施設、工場などの構造設計を行なう上で、最も重要な風荷重について、再検討しなくてはいけないでしょう。
太陽光発電モジュールを設備する架台の設計に用いられている、JIS規格における問題を明らかにし、実状に適した風荷重を算出し、太陽光発電システムの合理的かつ、耐風設計を見直す必要があるでしょう。これはこれからの太陽光発電の進歩にも重要な課題だと言えます。
とは言っても、自然災害の被害にあっているソーラーシステムは全体の1%~2%で少ないと言えます。この1%~2%の被害にあった場合の保険や補償を、契約時にきちんと確認する事がとても大事になってきます。
何よりも、契約する施工店が信頼出来る会社かどうか?
地元に根ざした施工販売店をいくつも比べて、しっかりと吟味していきたいものです。


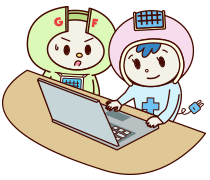
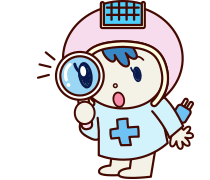
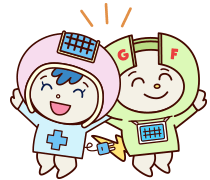
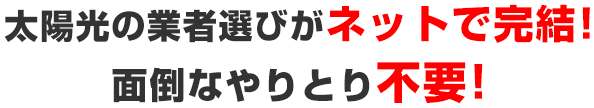
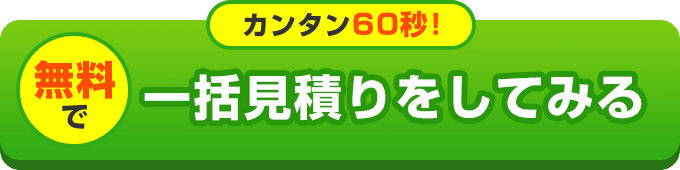
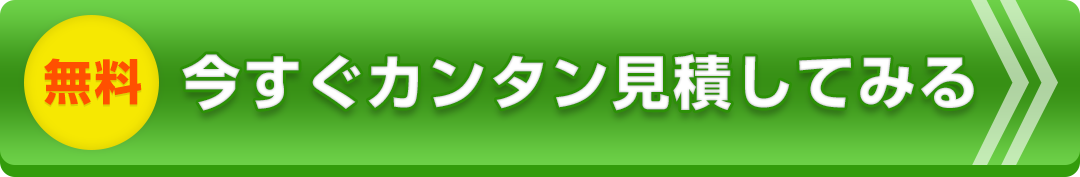

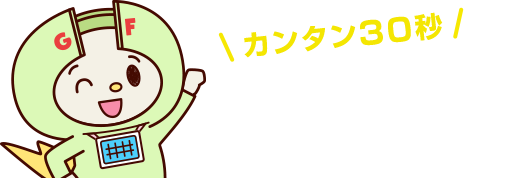
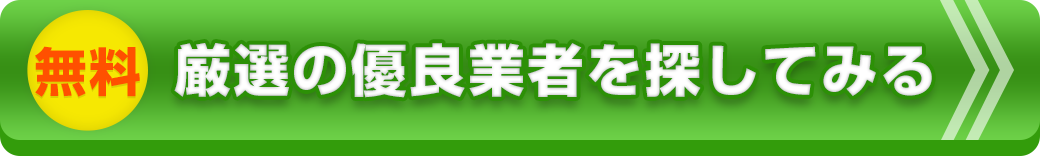
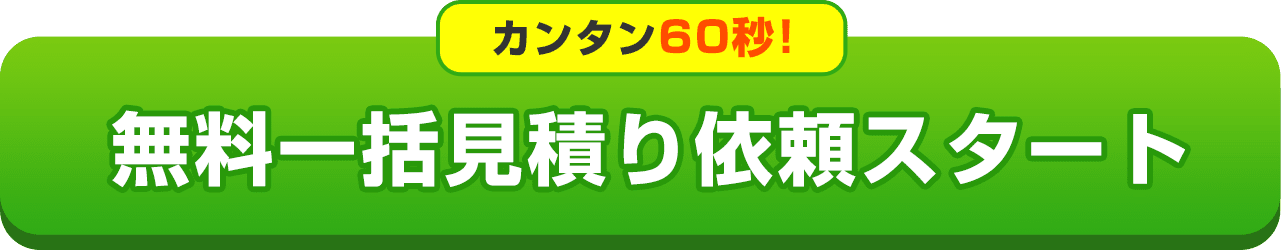
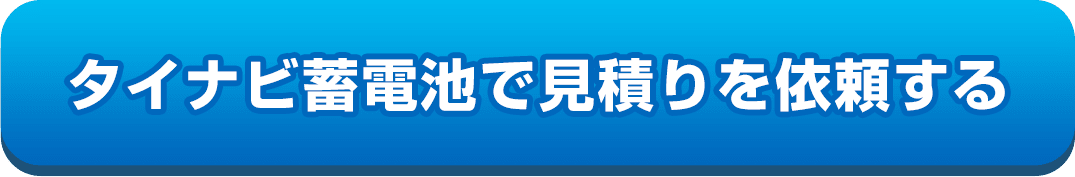


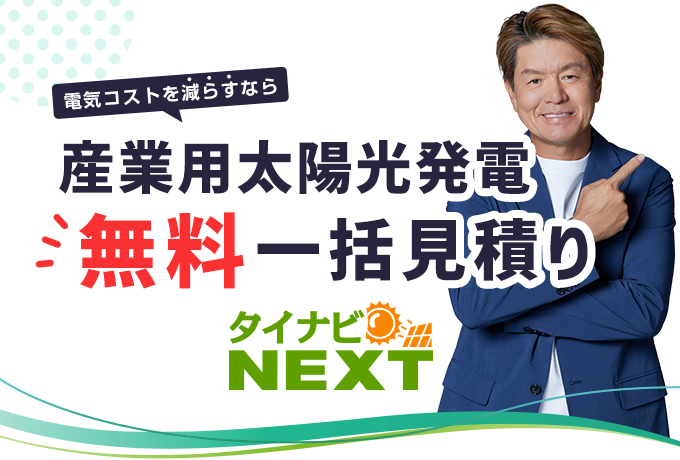
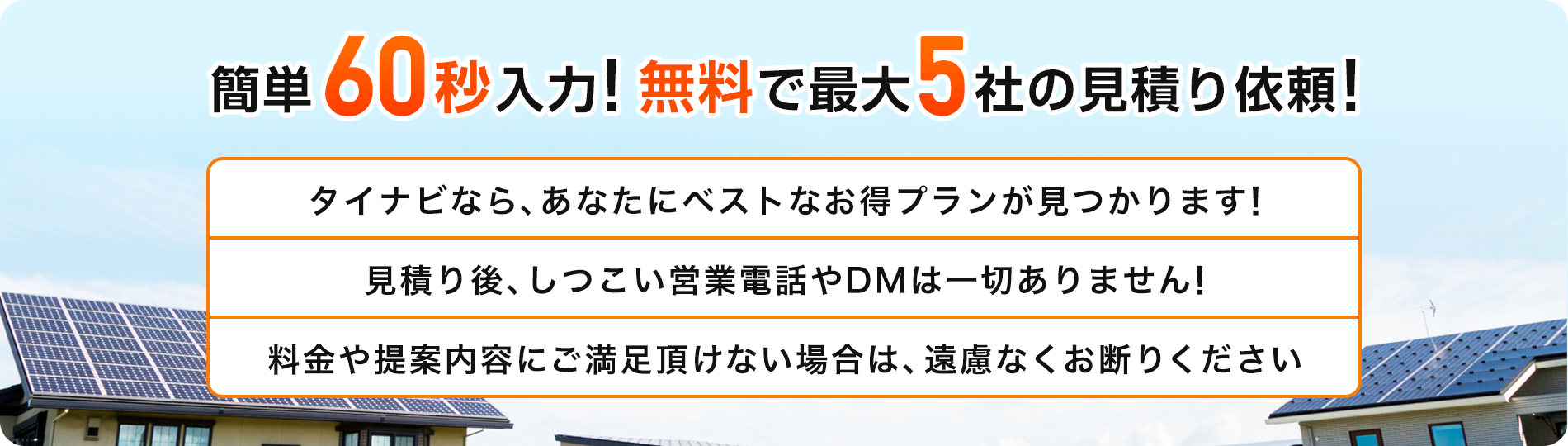
編集部おすすめ記事
家庭用太陽光発電とは?価格相場や初期費用を安く抑える方法、導入するメリット・デメリットを解説
【2025年版】家庭用太陽光発電と蓄電池の価格相場!セット価格がおすすめ!
【最新2025年度】太陽光発電の補助金はもらえる?補助金額や申請条件を解説!
【2025年】太陽光パネルメーカーおすすめランキング! コスパ・品質・価格で比較してみよう
【2025年最新】太陽光発電はやめたほうがいい5つの理由!後悔しないための完全ガイド
【初心者必見】太陽光発電を自宅に設置するメリット・デメリットとは?